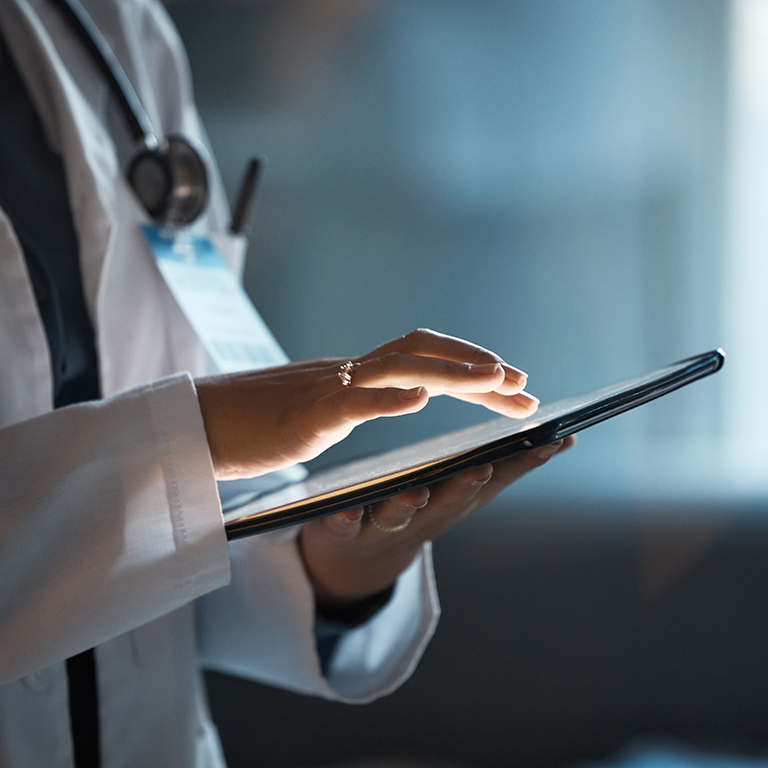

更新日:2023/07/23
介護予防の目的とは
高齢化が進む日本
2006年に行われた介護保険法の改正をきっかけに、介護予防の取り組みが本格化しました。高齢化が進む日本において、今後も増えていく高齢者ができる限り介護を必要とせず自立した生活を送れるようになるためには、早期から対策を講じる必要があります。そこで求められるのが介護予防であり、国は高齢者が健康的に生きていける社会の実現を目指しています。
対象者
介護予防の対象者は65歳以上の高齢者です。「要介護状態になることをできる限り遅らせる」「要介護状態になることを未然に防ぐ」「介護が必要な場合は状態の悪化を遅らせて改善を図る」といった目的に沿って、介護予防に取り組みます。具体的には、食生活の見直しや運動による身体機能低下の防止、食事や会話に必要な口腔機能の向上など、日常生活の質を高めるためのケアの総称を介護予防と呼びます。
あくまで予防を目的としたサービスなので、対象者は基本的に自立している高齢者、あるいは要支援1~2の高齢者です。すでに介護を必要としている高齢者については、介護度が低い状態からケアをすることで状態の悪化を防げると判断された場合に限り、介護予防サービスを受けられます。
介護予防サービスの概要
介護予防サービスと一口にいっても、種類は様々です。その中で最もポピュラーな介護予防サービスは、高齢者が住み慣れた土地や環境で自立した生活を続けられるよう、支援するものです。できる限り高齢者本人が自立して生活できることが前提であり、在宅での生活支援がメインです。
上記の介護予防サービスと同様に、住み慣れた環境の中で自立した生活を支援するものとして、地域密着型の介護予防サービスが存在します。種類や内容については自治体ごとに異なり、実施していない自治体もあります。基本的に、対象の地域に住んでいる高齢者のみを対象としたサービスです。
この他にも、地域支援型の介護予防ケアマネジメントも存在します。各地域において、要介護認定を受けていない高齢者や、要支援1~2の高齢者が対象です。介護度が上がらないように予防しつつ、住み慣れた環境の中で自立した生活を継続できるよう、支援します。将来的に介護や支援を必要とせず生活を続けられるよう、早期から支援するサービスです。
以上が、介護予防の目的や大まかな介護予防サービスの種類です。高齢化が進む日本において、介護予防の取り組みは必要不可欠です。そのため、それに携わる介護職の需要も大きく伸びており、あらゆる現場で人材を募集しています。
